
出産を機に一度働くことをセーブし、子育てに専念されたいというご家庭は多いかと思います。
筆者も産休をとらずに約10年勤めていた会社を退職しました。
当時、出産手当金、育児休業給付金といった産休・育休中に支給される手当はもらえないと、ある意味腹をくくって出した結論ではあったのですが、いろいろと調べると「どうやら出産手当金は退職後ももらえそうだぞ?」ということがわかってきました。
周りに産休を取らずに退職をした人もいなかったため、そんな情報を事前に知ることもできず、当然会社も教えてはくれなかったため、大慌てで申請をしたのを覚えています。
当記事では、筆者と同じように産休前に退職を検討していてる方向けに、出産手当金の支給条件や退職後も出産手当金を受給するための注意事項をご紹介したいと思います。
当記事がおススメの方
- 出産を機に退職を検討されている方
- 出産をし、退職をしたが出産手当金の受給を受けていない方
という方、ぜひ参考になさってください。
出産手当金とは?

出産手当金とは、健康保険の被保険者が、出産のために会社を休み、給与の支払いを受けなかった場合に受け取れる手当のことをいいます。
出産の日(出産の日が出産の予定日より後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は、98日)から出産の日後56日までが対象となっており、この期間に会社を休み、給与の支払いを受けていない日数分、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額を手当として受け取れます。
労働基準法では、6週間以内に出産する予定の労働者が請求した場合には、その者を就業させてはならないと規定しており、原則として産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけません。
その間、出産をする女性は無給となってしまうため、所得を補填することで安心して出産をすることが当制度の目的となっています。
出産育児一時金との違いは?
出産育児一時金とは、分娩にかかる費用や、入院費などの負担軽減を目的とした制度で、妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円))出産育児一時金が支給されます。
出産手当金は、会社で加入する健康保険(協会健保や健保組合など)の被保険者だけが支給対象ですが、出産育児一時金は、国保に加入している方や、被扶養者も支給対象となります。
産休をとらずに退職しても、出産手当金がもらえる人の条件。
出産手当金は、「健康保険の被保険者であること」が支給条件のため、退職をした場合は原則もらうことはできません。任意継続の場合も同様です。
ただし、一定の条件を満たす場合、退職後も出産手当金の支給を受けることができます。
全国健康保険協会によると、以下2点の条件を満たす場合には、退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができると記載されています。
(資格喪失後の継続給付)
被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
全国健康保険協会HPより
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
つまり、被保険者期間が1年以上継続してあり、出産以前42日前の時点で加入しており(退職していない)、退職日は出勤をしていなければ、出産手当金は受け取れるということです。

退職日を決める際はこの辺りにも注意しよう!
出産手当金の申請方法

会社に在籍中であれば、所定の部署が申請手続きについてアナウンスをしてくれたり、代理で処理をしてくれたりするケースもありますが、退職後の場合は、自身ですべて申請等を行わなければなりません。
必ず産前に健康保険組合に必要な手続きを確認しておきましょう。
具体的な申請手続き
各健康保険組合によって名称は異なると思いますが、申請方法は”出産手当金の支給申請書”といった書類に必要事項を記入し、提出をする形になります。
書類は健康保険組合のHPからダウンロードできる場合もあれば、TEL等で問い合わせをし取り寄せる必要がある場合もあります。
また、この書類には、出産をする病院の医師または助産師の方に記入していただく箇所もあります。前もって記入書類の取り寄せをし、産院に記入をお願いしておきましょう。
出産後、産院に記入をしていただいたら、当書類を健康保険組合に提出します。
いつまでに提出が必要?
出産手当金の申請は、産休開始の翌日から2年以内に申請をする必要があります。
比較的期限には余裕がありますが、産後、産院に記入いただいたら忘れないうちにすぐ提出してしまうことをおすすめします。
出産手当金を受給するにあたっての注意点
ここでは、出産手当金の支給についての注意点をご紹介します。

筆者もこの辺りがよくわからず、何度も何度も健康保険組合に問い合わせをしました。
有給消化期間は出産手当金の支給期間の対象にはなりません。
出産手当金は、あくまで出産に伴い勤務ができない(=所得がない)ことに対して所得を補填する制度のため、有給消化期間中は支給期間の対象にはなりません。
つまり、できるだけ”出産予定日42日前”の期間が削られないように退職日をセットできると、出産手当金の支給額も確保できるということです。
とはいえ、「出産日以前42日目が健康保険組合の加入期間」であることが支給の条件のため、その点も踏まえて検討する必要があります。
出産手当金の支給期間は(社会保険の)扶養には入れない可能性があります。
会社を退職し、出産をし育児が落ち着くまでは、一旦は旦那さんの扶養に入ることを検討されている方も多いかと思います。
しかし、扶養に入ってしまうと、出産手当金の支給を受けることができなくなってしまう可能性があります。
社会保険上の扶養に入るには、年収が130万円未満というのが一つの目安となります。
出産手当金についてもこの収入にカウントされてしまうため、支給額が多い方は注意が必要です。
また、支給額は年間ではなく支給額を支給期間で割った、日割りで見る組合が多いです。
その場合は、(出産手当金の支給期間のみ)退職後は一旦、加入していた健康保険組合に任意継続をするか、国民年金・国民健康保険に加入しておくことが必要です。
この辺りは、加入している健康保険組合によってルールや条件が異なるため、事前にしっかり確認をしておきましょう。

任意継続の保険料と国保の保険料どちらが安いかも調べておこう!
育児休業給付金は退職後ももらえる?
育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者の方が、1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当のことをいいます。
支給条件は以下のとおりです。
育児休業給付金は、職場復帰をすることが前提の制度のため、退職予定の方には支給はされません。
- 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
- 育児休業後、退職予定がない
- 育休中の就業日数が各1カ月に10日以下
- 育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていない
- 育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上
まとめ
当記事のまとめ💡
- 出産手当金は、産休を取らずに退職をしても一定の条件を満たせばもらえる
- ただし、退職後すぐ旦那さんの扶養に入るともらえなくなる可能性があるため注意!
- 育児休業給付金はもらえない
- 産前に必要書類を取り寄せたり記入をしたり、できる限り準備を進めておこう
退職後のことは手続きや申請、制度などあまり親切に教えてくれない会社がほとんどです。
筆者も産休をとらずに退職をしましたが、この辺りのことは全く知りませんでした。
退職後、扶養の手続きなどをなんとなくネットサーフィンして調べていたところ、退職後も出産手当金が支給されるということを知り、いそいで手続きをしました。
せっかくの制度ですから、”知らなかった”でもらえないのは悔しいですよね。
産後は子育てでバタバタし、他のことを考える余裕はなくなるかと思いますので、産前に諸々の申請に不備がないようたくさん調べてみてください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

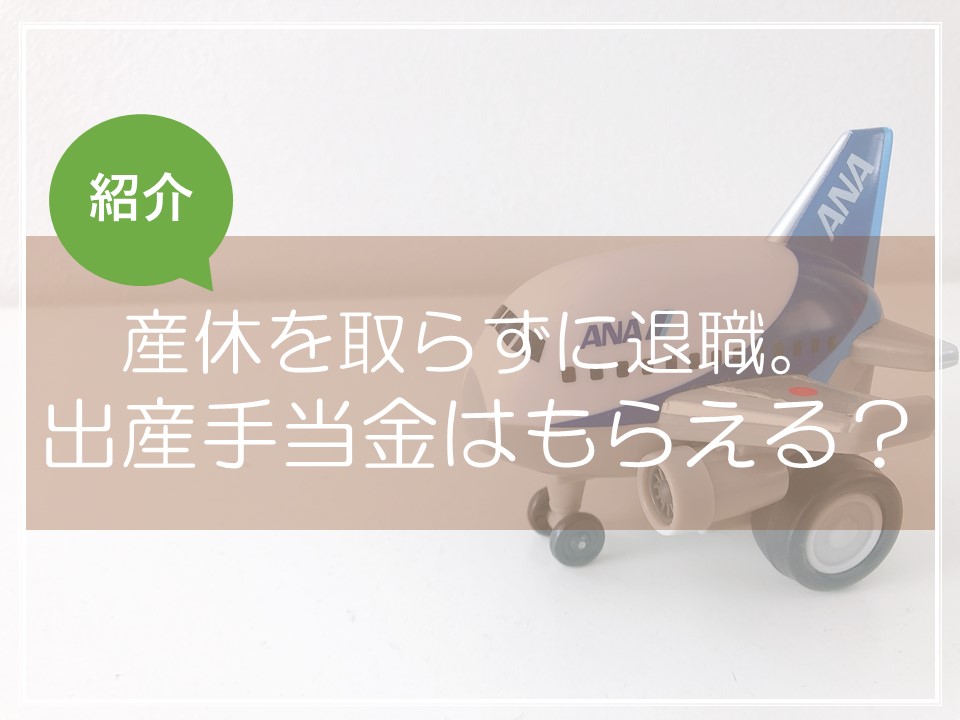

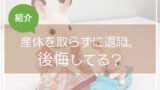



コメント