
共働きのご家庭だと、まだまだ送迎が必要な年齢のお子さんの場合、やらせてあげられる習い事の選択肢が限られてしまいますよね。
「プールに通わせたい!」「英語を習わせたい!」と思ってスクールを検索しても、そのほとんどが平日の昼間の時間…。仕事があるので通わせられません。
「でも、公文であれば近くに教室もあって通わせてあげられるし、家で勉強も見てあげられるから良いかも…。」とお考えの方、多いのではないでしょうか。
我が家も子供が3歳の頃、勉強に近いことを早い段階から遊び感覚で身に着けてもらえたら良いなと思い、公文に入会しました。
そして2年ほど継続をしていますが、正直結構大変です。(何度辞めようかと思ったことか。。。笑)
もちろんメリットも多く感じているからこそ継続をしているのですが、事前にこの大変さを知っておきたかった…と今では思います…。
当記事では、そんな筆者の失敗談から、共働き家庭が子供を公文に通わせるのであれば事前に理解しておいてほしいことを、まとめてご紹介します。
公文の入会をご検討中の方、ぜひ参考にしてみてください。
共働き家庭に公文(くもん)をおすすめしない理由3点。
共働き家庭に公文をおすすめしない理由は次のとおりです。
● 毎日宿題をやらせるのに一苦労。
● 公文を嫌がる子供が多い。
● 仕事帰りの入室だと子供も親も疲れてしまう。
ひとつひとつ見ていきます。
毎日宿題をやらせるのに一苦労。
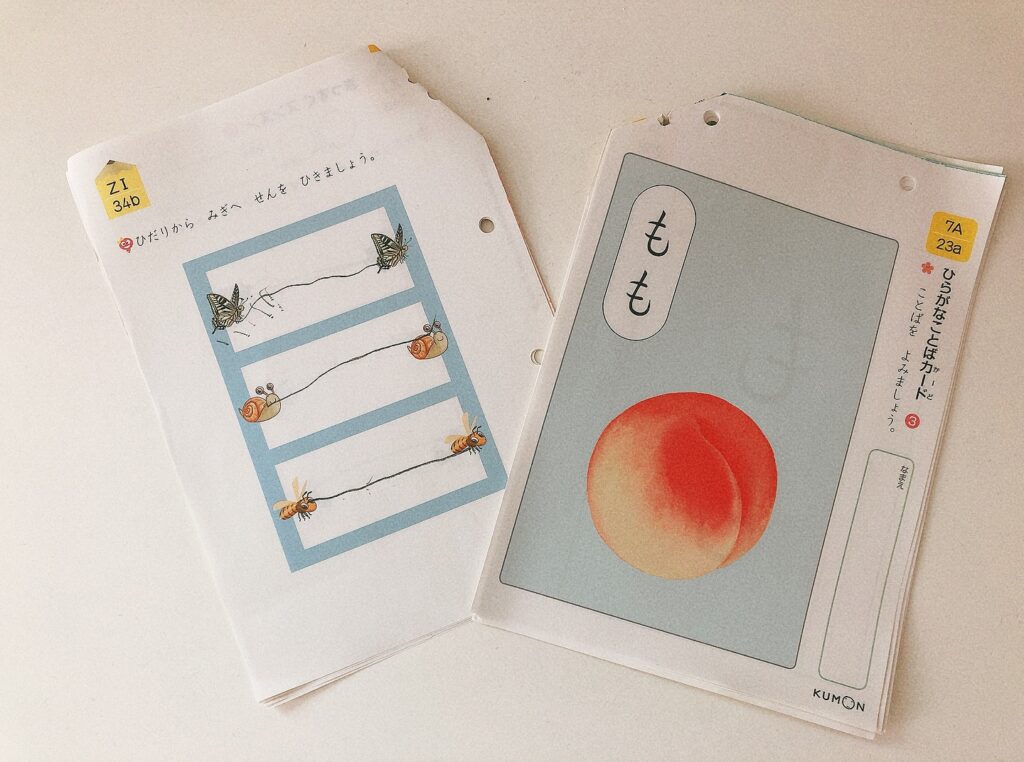
公文では学習用プリント●枚/日 を、宿題としてもらいます。
そして次の教室までにやってもっていき、採点をしてもらいます。
この宿題を毎日やらせることが本当に大変です。
我が家の4歳の子供は、20分~長いと1時間くらいかけて宿題をやります。
長い時の理由は、疲れていたり、やる気がなかったり、他のことをしたかったりと様々ですが、早く終わる日の方が珍しいのです。
毎日夕ご飯の支度をして、ご飯を食べさせて、お風呂に入れて、寝かせて…、この間に公文の宿題をやらせなければいけないので、時間的にも結構ハードになってきます。
小学生にあがると、学校の宿題もあったりするため、より時間的にハードになってきたりします。
公文を嫌がる子供が多い。

子供自ら進んで宿題をやってくれればいいのですが、なかなかそんな子ばかりではありません。
「公文やって~。」というと、「もう!今やろうと思ったのに言わないでよ~。」と言われる日も多くあります。笑
そんな中、かつ上記でも書いたように時間のない中、宿題をやらせなければならないため、親もイライラだってしてしまいます…。
とはいえ、子供も一日保育園や学校で過ごし、疲れて帰ってきて、また勉強か…となってしまう気持ちもわからなくはないのです…。
仕事帰りの入室だと子供も親も疲れてしまう。

宿題もそうですが、教室に通うのも大変なことのひとつです。
公文は19時まで、や20時まで…と、比較的遅くまで入室がOKな教室が多いため、共働き家庭には非常に心強いのですが、この時間から習い事に行くことが親御さんの負担になってしまうこともあります。
いつもより早く仕事が終わる日や仕事終わりの金曜日で今日だけ頑張れば!という日に教室に通えればいいのですが、そうでないと「行きたくなーい。」となってしまう日もあるかもしれません。
共働き家庭ならではの公文(くもん)のメリット5点。
通う曜日や時間を自分で選べる
公文は週2回教室に通い、日々の宿題(教材)を持ち帰ります。
週2回は教室によって曜日が異なるため、通いやすい曜日で空いている教室を選ぶとことができます。
また、時間も「【●時~●時】の間の好きな時間に来てください。」といったスタイルの教室が多いため、ある程度フレキシブルに時間を選択し、通うことが可能です。
- 夕方まで教室が空いている
- 多少通う時間が前後してもOK
という点は、仕事をしながら習い事を続けていくのに大きなメリットかと思います。
また、教室によっては入室・退室をすると、メールが届くシステムを入れてくれている教室もあるため、お子さんが退室したタイミングでお迎えにいったりすることもできます。
時間を有効に使うこともできるため、働くママ・パパには非常にありがたいですね。
なお、未就学児等の場合は時間がある程度決まっていたり、マンツーマンで先生が付くため、時間を決めましょうという教室もあるため、そこは先生にご相談されるといいと思います。
宿題交換のみ…等、自分のスケジュールに合わせて柔軟な対応が可能
「どうしても今日はこどもが疲れてしまった。」「帰りが遅くなってしまって、こどもがお腹をすかせている。」など、日によっては行けない日というのも出てくると思います。
そんな日は、宿題交換だけさせてもらったり、いつもはプリントを10枚やるところを5枚にしてもらったり、ある程度先生に相談することで柔軟に対応していただけます。
子供が小さい内はやる気にムラもあるため、気分が乗っている時は元気よく!そうではないときは、嫌がらない程度にサクッと済ませるのも長く続ける秘訣かもしれません。
どんな教材をやらせた方が良いか考える必要がない

公文は、その子その子にあった教材を先生が選択してくれます。
はじめは「本屋でドリルを買って、やらせてあげても一緒じゃない?」と思いましたが、「まだ書く力が弱いから運筆を継続しましょう。」といったことや、「●●の部分が弱いから、もう少し繰り返しここをやりましょう。」といったように、先生がしっかり進み具合を見てくれて適切な教材をやらせてくれるため、そこは通わせている大きなメリットだと思います。
何回も何回も同じプリントを繰り返し行うため、子供は飽きたりしますが笑、力にはなっているなと感じています。
先生が教材の学び方を適切にサポート

続きになりますが、ひらがなの書き方ひとつとっても教え方はさまざま。
私は、お恥ずかしながら書き順くらいしか意識して見てあげていませんでした。
すると先生から「書く順番に合わせてお母さんが、いーち、にー、さん、と書く長さに併せて声をかけてあげてください。そうすると書き順を正しく覚えていきますよ。」とアドバイスいただき、実践しました。
すると、本当に間違える回数が減りましたし、子供も楽しく書いてくれる時間が増えました!
一人でやっているとなかなかこういったことに気づけないため、このようなアドバイスをいただけることは非常にありがたかったです。
もちろん先生によってやり方は様々だと思うので、ぜひお子さんやご両親と相性の良い先生のいる教室を見つけられると良いと思います。
毎週通うことで宿題を終わらせなければならないという強制力を発揮
これはかなり大きいです。(笑)
どうしても忙しいと、「今日はいっか…。」という甘い誘惑に負けそうになります(親が)。
でも公文のメリットは、コツコツ地道にやることで確かな力をつけること!
ここでさぼったら公文をやる意味がありません。
毎週「宿題できませんでした。」で持っていくのは恥ずかしいし、月謝も勿体ないため、この強制力は通わせることの大きなメリットかと思います。
共働き家庭でも公文(くもん)を継続するコツ3点。
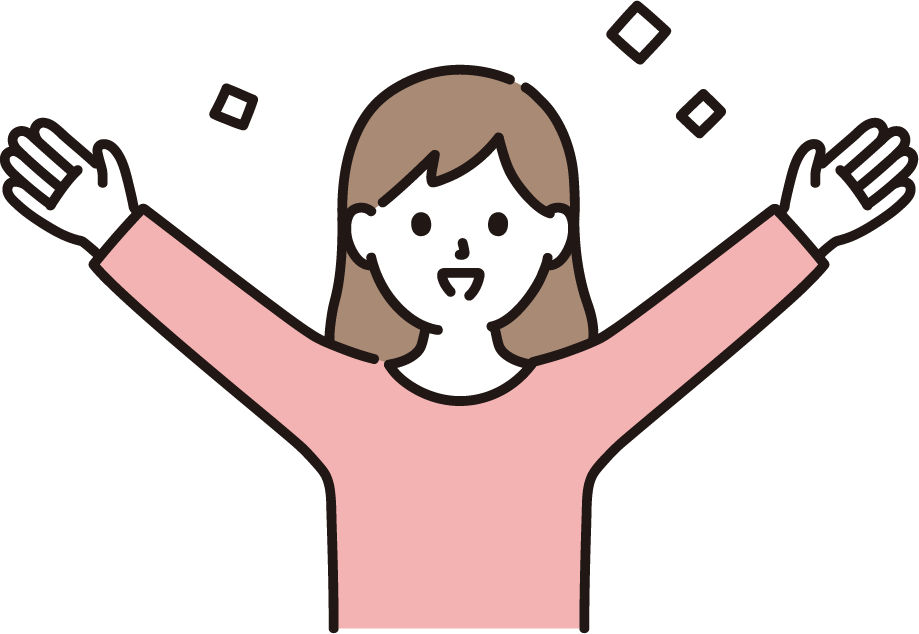
通い始めてから半年ほど経過したとき、やはり「くもんに通わせるのは辞めたほうがいいかも…。」と考えていました。
理由は子供がくもんをやるのも、いくのもとっても嫌がったからです。
原因は飽きです。
はじめこそ楽しく教材をやっていたのですが、だんだん同じようなことの繰り返しで飽きてきてしまいました。
「こんなことなら一度退会をして、もう少し大きくなったらやらせればいいか…。」などと考えたりもしたのですが、ここで辞めさせてしまったら、【せっかく今まで本人が身に着けようとしてきたものが無駄になってしまうかもしれない】【辞め癖がついてしまうかもしれない】と思い、宿題のやり方や子供への接し方を変えてみました。
ここでは公文を継続するコツを以下にまとめてご紹介します。
親がしっかり宿題を楽しくやるサポートをし、公文に嫌なイメージを持たせないようにする。
子供が小さいうちは特に、「宿題やりなさい!」だけでは動いてくれず、集中もできないことが多いです。
一日学校や保育園で頑張ってきたのだからなおさらそうかもしれません。
そんなときは一緒に横でプリントやってあげたり、会話しながらゲームっぽくして学習したりと、親がサポートしてあげるといいと思います。
我が家もなかなか子供が集中できないと、怒ってしまっていたこともあるのですが、それでは逆効果。どんどん勉強が嫌いになってしまいます…。
「できた!」という楽しい感覚を忘れないようにするためにも、できたらたくさん褒めてあげたり、できるだけ親がニコニコしてサポートをしてあげると良いのかなと思います。
公文をやる時間を決めスケジュール化し、宿題をやることを習慣化する。
毎日の学習の習慣化は非常に大事です。
毎日やる!と決めると決めないとでは、すんなりやってくれる難易度が全然違います。
「●時になったらやる。」でもいいし、「このTVを見たら…。」「youtubeを2つ見たら…。」などと、スケジュール化して家での決め事とするといいでしょう。
極力子供が好きなことの前、または後のほうがわかりやすく、子供もやる気がでるようでおすすめです♪
先生や教室の方針など、子供との相性は大丈夫かよく確認。
公文は教室によって本当に全然雰囲気が違います。
厳しめでキリっとした雰囲気の教室や、少しにぎやかで和気あいあいとした教室。
さまざまです。
入会を検討の際は通いやすさや曜日などもそうですが、ぜひ教室の雰囲気や先生の雰囲気も見ていただけたらと思います。
子供のことをしっかり見てくれそうか、学習の進め方で疑問や悩みがでてきたときに相談がしやすそうか…など、長く続けるのであれば、そういった点もしっかり見ておくことをおすすめします。
ちょっと公文は難しそうかも…。宿題を見てあげられる時間はとれなそう…という方へ。

「やっぱり我が家には難しそう…。」「自宅学習をしてあげたいけど、親がそこまで時間をさけなそうだな…。」という方は、タブレット学習がおすすめです。
スマイルゼミでは、未就園児でも一人で学習できる工夫が随所に散りばめられており、遊び感覚で楽しく学習ができるように作られています。
公文ではあんなに毎日宿題をやるのに難色を示す我が子も、スマイルゼミは毎日楽しくやってくれます。(それもこちらから何も言わずに…。笑)
学習の動機付けや楽しく学ぶということを学ぶ!という意味ではとても良い教材だと思います。
何より子供が楽しんでくれるのが一番です。
もしご興味がある方はこちらの記事をご参照ください。
まとめ:公文の継続は親の負担が半端ない。けれど学習の習慣化は必ず子供の力になります!
公文を自分の力にするには、毎日継続してコツコツ積み上げることが必須です。
けれどそれには親のサポートがとても重要です。(特に幼児期。)
公文を継続するのは本当に大変ですが、毎日続けることで必ず子供の力になります。
ぜひ毎日楽しくお子さんにあったやり方でサポートをしてあげてください。
以上、最後までご覧いただきありがとうございました。

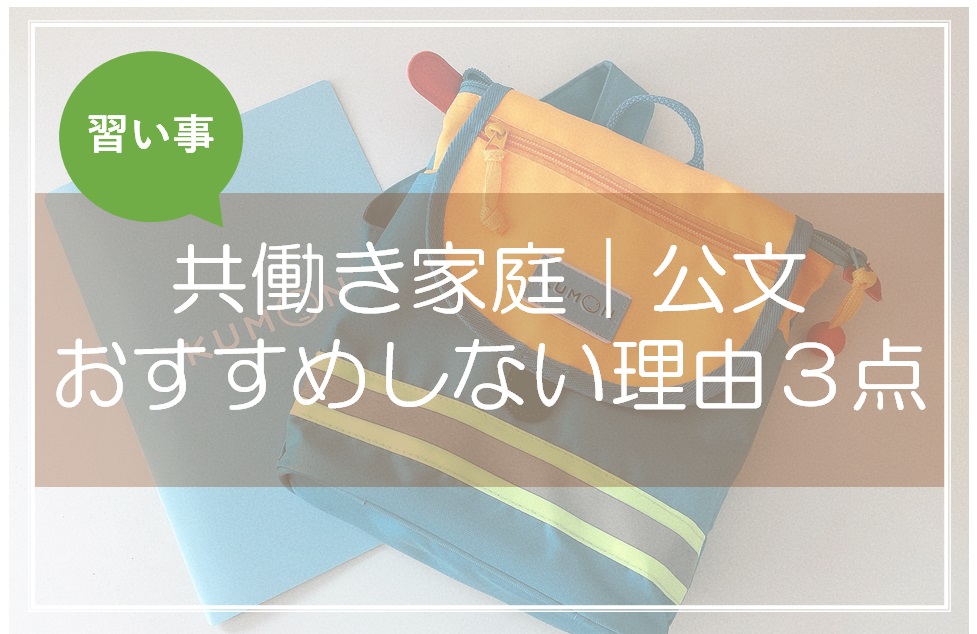
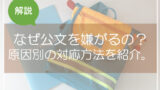
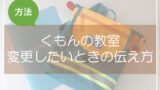
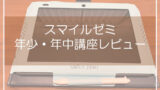
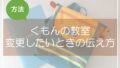
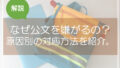
コメント